ノートに「知識」を書く必要はない!?
本に書いてある「知識」は読書ノートに書きません。本に書いてあるのなら本を見返せばいいだけです。知識のコピペノートをつくるのは時間の無駄です。
→気づき:古生物ってポケモンみたいだな
→アイデア:だったらポケモンカードならぬ古生物カードゲームをつくってみたらどうか
速く読む必要はない
「創造性」を第一に設定した知識で遊ぶ読書術では、速く読む必要はありません。
そもそも「速読術」と言って、目を速く動かしたり、ページを画像のように記憶するといったテクニックは信憑性がないものだと思ってください。人間の文章を処理する速度はある程度決まっているからです。
大事なのは速く読むことではなく、読んだ内容を何かに活かすことです。言ってみれば10冊の本を読んで、内容を丸暗記するよりも、1冊の本をじっくり読んで新しいものを生みだすことの方が大事です。
かといって全部読む必要もない
じっくり読むのが大事とは言えど、本に書いてあることをすべて読む必要はありません。なぜなら、本から得られるすべての情報が自分にとって必要な情報とは限らないからです。
本を読むときは辞書のような感覚で使うといいです。読む前に何となく目的を決めておき、必要な情報だけを集めてみるといいです。例えば、「科学的な研究による知識が知りたい」といった場合は、主張と根拠を中心に押さえていきます。「すぐにでも実践可能な知識が知りたい」という場合なら、理屈は後回しにして活用できそうな知識を中心に押さえてもいいでしょう。
目的を定めておけば、読む箇所自体が減るので速読しなくても効率的に読むことができます。「めんどうだな」と感じたら無理をせずに後回しにしていきましょう。
今は「難しいなぁ」と思える内容も、知識が増えれば楽しく読めるという場合もあります。苦しみながら読むと、記憶にも残りにくいですし、アイデアもひらめきません。
多読よりもひとつの本を「実践」
多くの本を読むよりも、本に書いてあることを1つでも実践することが大事です。
例えば、「運動中には記憶力が上がる」という知識を得たならばすぐに実践すべきです。
といっても、「実践しようとは思うけどなかなか行動に移せない」なんてこともあります。行動に移せないのは行動プランが漠然としすぎているからです。「運動をするのが大事」と思っていても、いつ・どこで・どのぐらいするのか定かでなければ、一生行動に移すことはできません。
行動するためのプランを立てるときにもノートが使えます。知識を実践するためのアイデアを出していきましょう。
→アイデア「いつも通っているスイミングプールを利用しよう。プールサイドに英単語帳を置いて覚えるのと泳ぐのを繰り返す」
→実践✔
ノートづくりのモチベーションを保つ工夫
そもそもノートづくりは、何度も見返してアイデアを重ねることが主な役割です。
見返すのが面倒という方は、見返すための動機づけをしましょう。オススメは見返すたびにチェックマーク(✔)を入れることです。
ノートにチェックを入れておけば、「後で見返したときにこんなに考えたんだなぁ」と分かります。チェックマークを増やすという目的ができるので、達成感を感じやすくなります。
また、新しいノートにしたときに表紙に現在の自分の能力値を示しておくのもオススメです。例えば、こんな感じ。
そして、ノート1冊分を書き終えたとき、そのときの自分とノートを書き始めたときの自分を比較すれば、成長度合いを知ることができます。
【今日のクエスト】ノートをつくって、今の自分の能力値を表紙に書いてみよう
【獲得経験値】


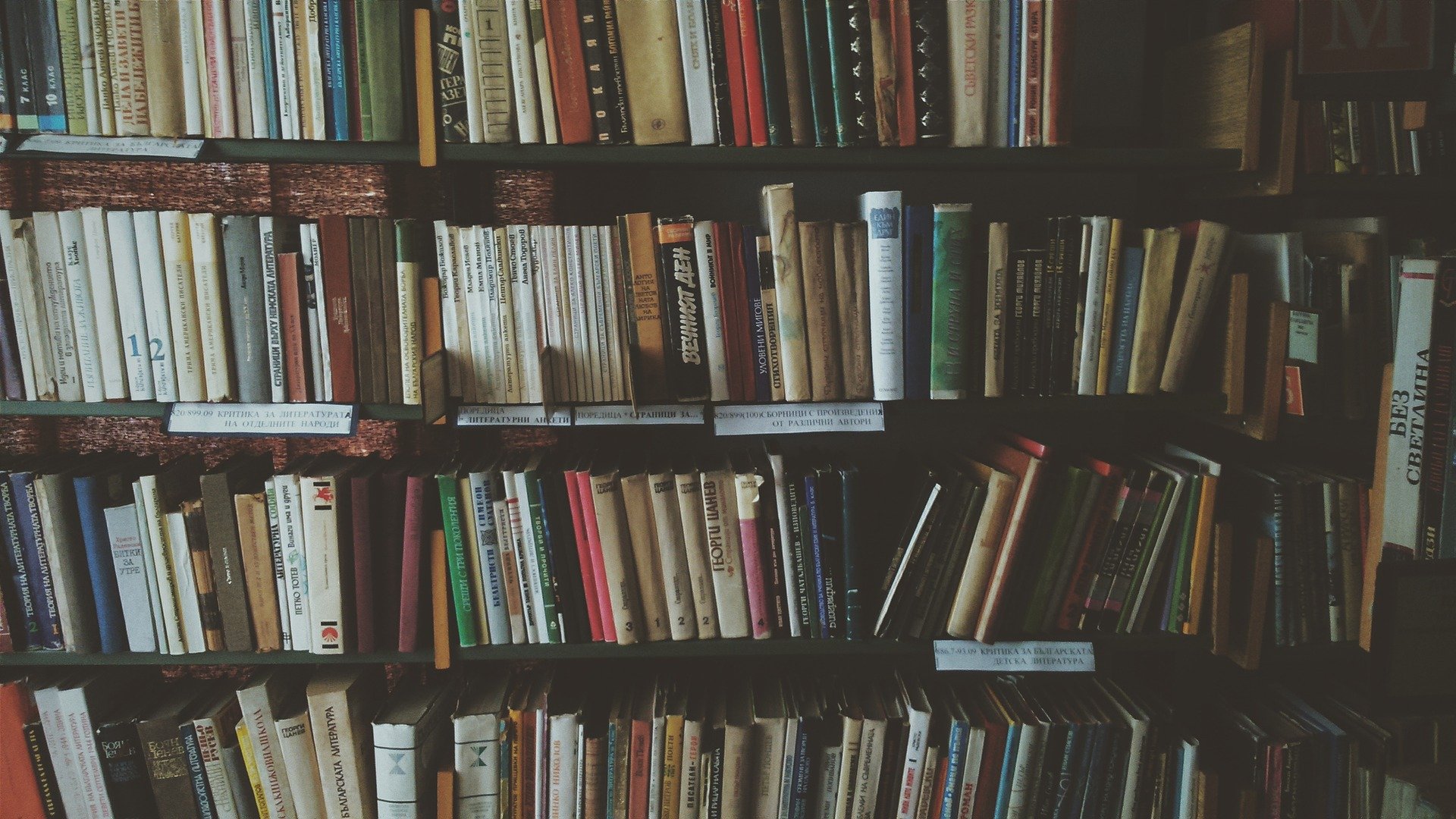

コメント